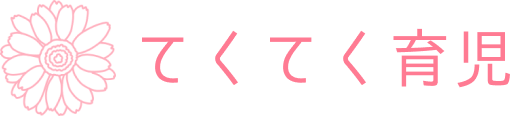赤ちゃんが生まれてすぐに受ける「新生児聴覚スクリーニング検査」。
この検査で「リファー(要再検査)」と結果が出たときの不安は、経験した人にしか分からないものです。
私の次男も、生後間もない時期にこの検査で両耳リファー(refer)と診断されました。
「うちの子、耳が聞こえないかもしれない…?」
そんな思いが頭から離れず、思い詰めないようにと考えながらも、赤ちゃんは音に反応しているか注意深く様子を見守る日々が続きました。
さらに医師からは、「念のため、できるだけ早く先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症の検査をしてください」と言われ、退院後すぐに大きな病院で検査を受けることに。
最終的に、CMV感染は「陰性」、その後の聴力検査も複数回の精密検査を経て異常なしと診断されました。
この記事では、私の体験を通して、
- 新生児聴覚スクリーニング検査の仕組み
- 「リファー」と言われたときの対応
- 実際に受けたCMV検査や精密検査の流れ
をまとめています。
同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
この記事では、結果的に息子が「パス」と診断された体験を紹介しています。
もし難聴と診断された場合でも、早く気づくことで言葉の遅れなどを防ぎ、必要な支援を受けることができます。
ご自身の状況によって、無理のない範囲でお読みいただければと思います。
新生児聴覚スクリーニング検査とは?
新生児聴覚スクリーニング検査は、生後すぐの赤ちゃんの聴力をチェックするための検査です。
赤ちゃんが無理なく受けられるように、眠っている間に短時間で行われます。
主な検査方法は2種類
- OAE(耳音響放射)
内耳の機能を確認する検査。検査時間が短く、スクリーニングでよく使われます。 - 自動ABR(自動聴性脳幹反応)
脳の反応を測定する方法で、より詳しく調べる際に使われます。
次男の検査はABRの方でした。
新生児聴覚スクリーニング検査の結果は、「パス(問題なし)」か「リファー(要再検査)」のどちらか。
「リファー」と言われたからといって、すぐに難聴があると確定するわけではありません。
あくまでも「今回の検査できちんと反応していなかったから、聴力の精密検査をしてね」という意味です。
なぜ「リファー」と言われるの?
「リファー」となる理由には、検査時のさまざまな要因が関係していることがあります。
よくある原因
- 耳の中に羊水や胎脂が残っている
生まれてすぐは耳の中に不要なものが残っていて、音がうまく伝わらないことがあります。 - 脳の発達が未熟で、検査への反応が弱いことがある
- 赤ちゃんが動いていた・周囲の環境が騒がしかった
検査のタイミングや環境も結果に影響することがあります。 - 耳の形状や個人差
機器がうまくフィットせず、正確に測れないこともあります。
ただし、難聴の可能性がある場合もあるため、必ず精密検査を受けて確認することが大切です。
「CMV感染症の検査を」と言われたとき
新生児聴覚スクリーニングで両耳リファーとなった次男。
リファーと伝えられたその場で、医師から「大きい病院で、先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症の検査も受けましょう。予約しますね」と言われました。
先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症とは?
サイトメガロウイルス(CMV)は、多くの人が保有しているウイルスで、大人が感染してもほとんど症状が出ません。
しかし、妊娠中に初感染した場合、赤ちゃんに影響が出ることがあります。
主な症状には、
- 難聴
- 発達の遅れ
- 黄疸や肝機能障害
などがあり、中でも難聴はよくある兆候とされています。
検査の流れ(尿検査)と注意点
私たちは退院後すぐ、紹介された大病院で次男の尿検査を受けました。
CMV検査は生後3週間以内に行う必要があります。
それ以降だと、後から感染したのか、胎内で感染したのかが判断できなくなるためです。
退院した直後で産後の体も回復していなかったので、待合室で待つ時間は大変でした。
また、オムツに採尿パックをつけて検査用の尿を取る必要があったのですが、なかなか出ないので授乳をしてみたり、夫が抱っこしてウロウロして時間をつぶし、やっとギリギリの量が取れました。
約3週間後に伝えられた結果は「陰性」。本当にホッとしたのを覚えています。
我が家の場合は産婦人科で先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を勧められましたが、ネットで調べるとCMV検査を受けるように言われなかった人もいるようなので、病院の判断によるのかもしれません。
実際に受けた4回の精密検査【生後1ヶ月〜1歳】
CMV検査が終わり、産婦人科で1か月健診をした後。
赤ちゃんの詳しい聴力検査ができる、県の小児医療センターの耳鼻咽喉科に紹介状を書いてもらい、精密検査を受けに行きました。
精密検査の回数は病院によると思いますが、次男の場合、合計4回の精密検査を受けました。
生後1か月過ぎ:初めての精密検査(ABR・OAE・BOA)
最初の精密検査は、生後1か月の頃でした。
実施された検査
- ABR(聴性脳幹反応)
自然に寝かしつけた後に、赤ちゃんの額や頬、首に電極をつけて脳波の検査。音に対する脳の反応を測定します。 - DPOAE(歪成分耳音響放射)
耳音響放射(OAE)の一種で、専用の機械を耳に当てて、音に対する蝸牛内の有毛細胞の反応を測定する検査。 - BOA(聴性行動反応検査)
楽器や物の音に赤ちゃんが反応するかを観察する簡易検査も行われました。
📌 参考:乳幼児聴力検査|滋賀県ホームページ
小児難聴|奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学
この時点で、いずれの検査でも「聴力に問題ない」との診断を受けました。
首がすわった頃(生後4〜5か月):2回目の検査
赤ちゃんが音への反応を少しずつ示すようになるこの時期。耳鼻科で2回目の検査を受けました。
実施された検査
- COR(条件詮索反応聴力検査)
音が鳴るとぬいぐるみが動き出し、赤ちゃんがその方向を見るかを確認します。音に対する認知の発達もチェックできる検査です。 - DPOAE(歪成分耳音響放射)
1回目と同じ機器を使って検査。
📌 参考:福井県の乳幼児聴力検査ガイド
このときも異常は見られませんでしたが、医師からは「念のため10か月健診のあとにも確認しましょう」と言われました。
10か月健診後:3回目の検査
市の10か月健診のあとに、再び耳鼻科を受診。前回と同じ内容の検査が行われました。
ただ鼻風邪が治ったばかりで中耳炎になっていたことが判明。中耳炎だと検査がうまくできないので、治ってから後日再受診しました。
実施された検査
- COR(条件詮索反応聴力検査)
- DPOAE(歪成分耳音響放射)
この時点でも「問題なし」との結果。
「最後に脳波の検査をするので、それで問題なければ検査はおしまいです。」と言われ、次の脳波の検査の予約をすることに。
この頃には、少しずつ安心感が増してきていました。
1歳過ぎ:最終的な検査(ASSR)
病院の予約枠の都合で、最後の検査は1歳を過ぎた頃に行われました。ここでは、さらに正確性の高い検査が加わりました。
実施された検査
- ASSR(聴性定常反応)
脳波を測定する聴力検査で、ABRよりも細かな聴力の程度を測定できます。 - COR(条件詮索反応聴力検査)
このASSR(聴性定常反応)では、睡眠導入剤が使われました。
次男にスポイトで薬を飲んでもらって、親が寝かしつけ。
検査自体は1時間くらいで終わりましたが、その後目が開いたのを医師が確認する必要があり、起こすのに苦労しました。
医師からは
「脳波の検査も問題なかったので、もうこちらでの検査はおしまいです。これからは、市の定期健診に委ねようと思います。また何か気になることがあったら来てください」
と言われ、ようやく一区切りがつきました。
まとめ
新生児聴覚スクリーニングで「リファー」と言われたときの不安は、私も本当によくわかります。
私の息子は結果的には、精密検査で聴力に異常がないと診断されました。
でも、もし難聴が確認されたとしても、早く気づくことで適切な支援につなげることができると知り、心が少しずつ前を向いていたのも事実です。
難聴に気付かないままだと言語発達に遅れなどがでてしまうので、
「もし難聴だったとしても、赤ちゃんの時に気付いたらすぐに難聴の対策をしてあげられるから、スクリーニング検査をして良かったよね」
と夫と話していました。
言葉の発達や日常生活の中でのサポートなど、必要な支援を受けながら育っていける道はたくさんあります。
このブログが、同じように不安を抱えている方にとって、少しでも安心につながるきっかけになれば嬉しいです。
あなたと赤ちゃんが、これからも穏やかな毎日を過ごせますように。